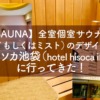【使ってみた?】ChatGPTの始め方と使い方。スマホでも手軽に使える「対話するAI」
【景品表示法に基づく表記】本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。


カイエダです。
各種メディアでも話題になっている、2022年11月に登場したChatGPT(チャットジーピーティー)。
もう使ってみましたか?
これから!という方のために、この記事では、ChatGPTについて解説してみます。
最後に私の意見もまとめてみました。
使うときの、参考になさってください。
この記事の目次
そもそもChatGPTとは、なんぞや
ChatGPTは、OpenAI※1によって開発された自然言語処理技術を利用したチャットボットです。

(※1)OpenAIとは、人工知能の研究・開発・普及を目的とした、非営利の研究機関のことです。
2015年に設立され、創設メンバーには、イーロン・マスク氏やサム・アルトマン氏などがいました。
ちなみに、ChatGPTとの対話にテーマの制限はないようです。
使う側の質問やリクエストに対して、AIが適切だと判断した回答が返ってきますが…。

ChatGPTが学習しているのは2021年末までの情報だそうです。質問によっては回答が最新のものではない可能性もあります。
どんどん利用されていくと、さらに学習していくのでしょうね。
GPTとは、「Generative Pre-trained Transformer」の略です。
Transformerという機械学習のモデルを用いて、大規模な自然言語処理の事前学習を行ったモデルのことを指します。
このGPTを用いて大量のテキストデータを学習し、人工知能による対話を実現しています。
ChatGPTは、ユーザーからのテキスト入力に応じて、自動的に回答を生成します。
回答は、自然な言葉遣いで返されますので、人間との対話のように自然な印象を受けます。

日本語もとても自然です。
ChatGPTは、医療、教育、カスタマーサポートなど、すでに様々な分野で利用されています。
利用することで、自然な言葉遣いでの自動応答、会話ログの分析、ユーザーのニーズの把握などが可能になります。
ChatGPTを使う方法

それではChatGPTの始め方と簡単な使い方を、解説してみます。
ChatGPTは、とっても簡単に使えますが、公式サイトは英語で書かれているため、抵抗感を感じる方もいるかもしれません。
難しい作業はありませんので、順番に進めてみてください。
画面キャプチャはパソコンのものですが、スマホでもほぼ同じ工程で使えるようになります。
ChatGPTにアクセスする
まず、ChatGPTにアクセスします。Webブラウザを開き、次のURLに行ってみます。
https://chatgpt.com/
公式サイトにアクセスすると、まずこの画面が表示されます。

初めて登録する方は「Sign up」を選んでください。
メールの入力

「Create your account(アカウントの新規開設)」という画面に変わります。
「Email address」の欄に登録したいメールアドレスを記入し、「Continue」をクリックします。
Googleアカウントやマイクロソフトアカウントを使って登録することもできます。
任意のパスワードを入力
メールアドレス入力>「Continue」のあとは、パスワード入力が求められます。
入力したら「Continue」ボタンをクリック。

届いたメールを確認

すると「メール送ったから、確認してくれーい」という画面が登場。
ちゃとメールが届きます。
問題ないようであれば、「Verify email address」ボタンをクリックしましょう

氏名の入力

次に氏名を入力します。
こちらはアルファベットでも日本語でもどちらでも問題ありません。
「Continue」をクリックすると登録が完了です。
ちなみに下の注釈部分には
Continueボタンをクリックすると、ChatGPTの規約に同意したとみなされます。
また18歳以上であることを確認したことになります。
というような内容が書かれています。
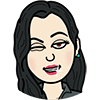
18歳以下、登録ダメなんですね…。
なんでR18?
電話番号の入力から認証コードを入力

まだまだありますよ…。
最後に電話番号を入力します。
入力後、SMSに認証コードが送られてきますので入力します。

けっこう個人情報求められるんです。

最後の質問に答える

質問に答えます。
訳は次のとおり。
無難にいく、ならば「I’m exploring personal use(個人利用を検討中です)」がよいかもしれません。
- How will you primarily use OpenAI?(主にどのように OpenAI を使用しますか?)
- I’m building a product or feature(製品または作品をつくります)
- I’m exploring personal use(個人利用を検討中です)
- I’m conducting AI research(AIの研究をしています)
- I’m a journalist or content creator(私はジャーナリストまたはコンテンツ作成者です)
登録完了!ログインし直してみると…
ようやく登録が完了しました。
登録後、さあ使ってみましょう!と入力画面に入ろうとすると、次のような注意が出てきます。
それぞれ翻訳を対で載せておきますね。

This is a free research preview.
これは無料の調査プレビューです。
Our goal is to get external feedback in order to improve our systems and make them safer.
私たちの目標は、システムを改善し、より安全にするために、外部からのフィードバックを得ることです。
While we have safeguards in place, the system may occasionally generate incorrect or misleading information and produce offensive or biased content. It is not intended to give advice.
安全対策を講じていますが、システムが不正確または誤解を招く情報を生成し、攻撃的または偏ったコンテンツを生成することがあります。アドバイスをすることを目的としたものではありません。

How we collect data データの収集方法 Conversations may be reviewed by our AI trainers to improve our systems. 会話は、システムを改善するために AI トレーナーによって確認される場合があります。 Please don't share any sensitive information in your conversations. 会話で機密情報を共有しないでください。

We’d love your feedback!
フィードバックをお待ちしております。
This system is optimized for dialogue. Let us know if a particular response was good or unhelpful.
このシステムは対話用に最適化されています。特定の回答が良かった、または役に立たなかった場合はお知らせください。
Share your feedback in our Discord server.
Discord サーバーでフィードバックを共有してください。
テキストを入力してみましょう
画面に表示されたテキストボックスに質問や文章を入力します。
ChatGPTは自然言語処理を利用しているため、自然な言葉で質問や文章を入力することができます。

テキストを入力したら、Enterキーを押してChatGPTとの会話を開始します。
ChatGPTは、入力に応じて自動的に回答を生成し、テキストボックスに表示します。
どんな答えが返ってくる?

ちなみに「東京のオススメのサウナはどこですか?」と入力してみましたら…。

けっこう丁寧な答えが返ってきました。
もちろん、正確な答えが必ずしも返ってくるか…、というとそんなことはないです(学習中だそうなのでね^^)。
最終的な正確性のチェックは、自分の力でおこなう必要があります。
その他注目のAIサービス
Microsoftの検索エンジンである「Bing」も、新しくなったんですよね。
私は少しだけ注目しています。

実際の運用にはまだまだ課題はありそうですが、Bingもシェアを増やしていきそうです。
Google、少し遅れてるんですよねこの分野。
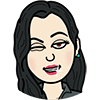
果たして今後、どうなっていくのか。
楽しみですね。
まとめとして
ChatGPTは2022年11月に登場した新たなサービスです。
上述したとおり、まだまだ開発途中な部分もあります。
どんどん学習していって、さらに使いやすいサービスにアップデートしていくでしょう。
AIは、今のところ、あくまでも人間の活動を助けてくれるツールです。
どんな答えを導き出すか、またどんな使い方をするのかは、あなた自身にかかっています。
求む!おもしろみ!
私は、ChatGPTで導き出された文章をそのままブログで使ったとしても「おもしろみ」が足りないなと感じました。
人は正確さや正義だけを求めているのかというと、そういうものではないですよね。
もちろん嘘はいけませんので、裏付けを取った上での「おもしろみ」である必要がありますが。
文章でも動画でも画像でも音声でも、そこになんらかの「不完全な愛すべき人間味」があるからこそ、おもしろいのではないでしょうか。
それをおもしろいかおもしろくないかを判断するのも、最終的には人です。
私たちはパソコンの使い方やスマホの使い方を覚えてきたように、これからはAIの使い方も覚える必要があります。

うまく、使いこなしていきましょうね!