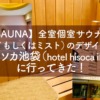完璧主義だと、実は完璧にならない。自分に優しくしながら成長していく4つのコツ
【景品表示法に基づく表記】本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。


カイエダです。
たくさんのお客様と接して思うのは、多くの方が「じゅうぶんできているのに完璧主義すぎて、最初の一歩をふみだせていない」ということです。
実は、完璧にこだわると、完璧になれないという逆説的なことが起こりやすいのです。
この記事では、なにごとも100点を目指さなくていいんだよ〜という考えを、カイエダの経験をもとにお伝えしていきますね。
この記事の目次
失敗したくない、という恐れや不安から完璧主義になる
- 文章が下手だからブログがかけない
- ITが苦手だからメルマガなんて書けない
- 時間がないからランディングページが作れない
- 考えすぎて、進めなくなってしまう

個別相談やセミナーで、この手の「言い訳」をむちゃくちゃ聞いてきました。
少し厳し目の言い方です。
もちろん気持ちはわかるんです。
言い訳ですよ、と正論で指摘すると、逆ギレしたり、そんなことはない、とアドバイスを素直に受け取れなくなってしまう方も多いです。
大抵私のメルマガを速攻解除なさいます(笑)
こうした「言い訳」が生まれる背景にはどういった感情が働いているのでしょう。
自分の経験もふまえ分析してみると「ぜったい失敗したくない!」という「恐れや不安」が働いています。
ぜったい失敗したくないから、やる前から100%のできあがりを自分に求める結果、100%のできあがりにならないとわかると、途端に取り組めなくなってしまうのです。
「だめだ……」と自分を責めてしまうのですね。

「いやいや、最初から100%なんて、期待していませんよ」という方も多いのですが、完璧主義の人には「失敗を恐れる感情」が隠れているのがわかります。
完璧主義の人にみられる「先延ばし」の傾向
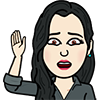
完璧主義の人は、結果として「先延ばし」してしまう傾向にあります。
たとえば……。
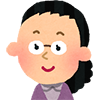
私は講師となりましたが、完璧にできるようになるまで、人前に立ちません

起業して告知をしていきたいですが、もっと痩せてから、自分の写真を世の中に出します
(これよく聞きます)
といった思いにとらわれて、最初の一歩が踏み出せなくなってしまうのです。
結果として「できるようになってから」「痩せてから」と自分で想定した「本番」の経験を積まないと、頭の中だけでシミュレーションするだけとなり、実体験が少なくなってしまいます。
実体験を積んだり、反応を得る経験をするからこそ、次の一歩を重ねていけます。
一歩をふみだせないと、結果「よくなる練習」を積めなくなってしまいます。
練習を積めないと、なかなか技量が上がらず本番を迎える段階には永久に移れない、といった悲劇がおこります。
完璧じゃなくてもいいや!という人たちは、たとえ最初は質が低くても、気軽に第一歩をふみ出します。
失敗することすら「うまくいかないことも勉強だ!」「挫折もネタになる!」と人知れず楽しみながら経験を重ねていけるのです。
すると最終的には、着実に技量があがっています。
完璧主義者は、非完璧主義者の技量の上がった状態だけをみて、指をくわえて眺めつづけます。
「あいつはできなかったのに、いつのまにかうまくいっている。自分はこんなもんじゃない。もっとできるはずだ」と自分にさらに期待し、また100%を求めてしまうという「負のループ」を繰り返します。

いいことひとつもない……!
人間は完璧じゃない!ことを前提に、とはいえ開き直らずに

人間は、そもそも完璧にはできていません。
たとえば、子どもができたら突然「お父さん」「お母さん」になりますが、お父さんお母さんも0歳なんです。
親としてスタートする年齢は、子どもと実年齢が一緒なんですよね。
だから最初からすべてわかるわけがないし、うまくいかなくて当たり前だ!と思って過ごしていかないと、発狂してしまうでしょう。
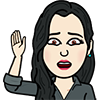
だからと言って……!

私は完璧じゃないから、できなくていいんだ。
できないからやらなくていいんだ〜

というワケではありません。
開きなおって、努力を怠ってしまっては本末転倒。
「完璧主義を手放す」ことは「思考や行動を停止する」ことや、「現実逃避」ではまったくありません。
動きながら考え、自分に優しくしながら成長する4つのコツ
完璧主義であるために結果的に、何事も先延ばししてしまう傾向を手放すためには、どういう心構えでいればいいのでしょうか。
完璧主義から自分を解放するためには「動きながら考える」といいですよ。
もちろん猛スピードである必要はありません。
すべて自分のペースでいいです。
自分を適度に優しく扱うことがポイントです。
動きながら考えることが普通になってくると、成長中に常に改善ができるので、さらに成長が加速されます。
動きながら考え、自分に優しくしながら成長するコツは以下の4つです。
- リフレーミングを習慣にする
- 目標はもっともっと分解して、小さい達成感を感じまくっていく
- 目標達成したときの、自分用のご褒美を勝手に設けてみる
- たまに情報を遮断する

ひとつずつ解説していきます!
1)リフレーミングを習慣にする
リフレーミング!
カウンセリング用語ですので、まずは用語解説から。
リフレーミング(reframing)とは、ある枠組み(フレーム)で捉えられている物事を枠組みをはずして、違う枠組みで見ることを指す。
(中略)
西尾和美『リフレーム 一瞬で変化を起こすカウンセリングの技術』によると、「リフレームの目的は、今までの考えとは違った角度からアプローチしたり、視点を変えたり、焦点をずらしたり、解釈を変えたりと、誰もが潜在的に持っている能力を使って、意図的に自分や相手の生き方を健全なものにし、ポジティブなものにしていくこと」(32p)とのこと。

私のオススメは、悪い事柄を、良い言い方に変えることです。
「あなたの弱みを売りなさい」という本の紹介をした動画でも話したことがあるのですが、弱みは強みに変えられます。
ネガティブなことも、ポジティブな言葉に切り替えれば、強みに生まれ変わりますよ。
リフレーミングにオススメなのが【短所を長所に変えたいやき】という、かるたカード!
このかるたゲームはネガティブな言葉を、ポジティブな言葉に頭の中で考えてかるたを取っていくもの。
たとえば
「ずうずうしい。ずうずうしい彼からのデートの誘いは断れない」
と読んだ後、「ずうずうしい」というワードを良い意味で言うと……?と考え「押しが強い」というカードを探し選びます。
リフレーミングの習慣付けは、仲間やパートナーの協力があると進む
たとえば私の例。
私は、とってもおでこが広くて(笑)、小顔の女の子と隣で写真を撮ると、むちゃくちゃ巨顔に見えるんです。
それを夫に「顔が大きくてやだなー」と言ったら、夫は

大きいなんて、高級な証拠じゃないか!
ぬいぐるみだって大きい方が高いじゃん!
いいじゃん!大きくて(笑)
お前はなんて、高級なんだ!!!
と、意表をついた返しをしてきたのです。
大笑いしました(笑)
このように、パートナーに、無理やり前向きな捉え直しをしてもらうと、自分でもリフレーミングが少し習慣化できます。

また仲間と「無理やりリフレーミング週間」などを設定し、マイナス表現をいかにプラス表現に変えていけるかを言い合うチャットやLINEグループなどを設定してもおもしろいのではないかな、と思います^^
2)目標はもっともっと分解して、小さい達成感を感じまくっていく
最初から完璧を求めてしまう人は、最初から成功した自分しか許さない傾向があります。
まず目標を決めたら、その道のりを細かく分解していき、1個ずつクリアしていくことをオススメします。
なぜなら「ローマは1日にしてならず」だからです。
どんな成功者でも、すぐに成功できたわけではありません。
小さな目標をコツコツ達成してきたからこそ、今があるのです。
そしてひとつひとつ、目標をクリアしていく達成感は、とても気分のいいものです。
目標の分解、オススメですよ。
私の感じた話をはさみます。
先日、芸人のバナナマンさんのコントライブに夫と出かけてきました。
バナナマンは今やテレビで見ない日がないくらいおふたりとも売れっ子です。
忙しいスケジュールの中でも、毎年、コントライブは数日間、開催しているのです。
コント職人としての、芸人としての意地なのでしょうね。
ファンクラブ会員でもチケットが取りにくいライブです。
そんな中、ついに夫がチケットをゲット!
しかも前から3列目!
ライブは、これまでたくさんのお笑いライブを見てきましたが、どんなライブよりも素晴らしかったです。
観劇後感じた圧倒的な「プロ」感。
仕事ってこうあるべきだな、と。
アドリブでごまかさないプロとしての意地と実力と才能。
圧巻でした。
もちろんバナナマンも、テレビにまったく出れない時期だってあったんです。
最初から売れっ子だったわけではありません。
どんなに目指しても、最初からバナナマンになれるわけはないのです。

自分ももっと人知れず必死にもがいて、クールに決めてるプロであろうとバナナマンのライブをみて肝に銘じました!
そのためにも、目標分解してひとつずつクリア!ですね。
3)目標達成したときの、自分用のご褒美を勝手に設けてみる
2)と合わせると効果的!です。
小さな目標達成のたびにでもいいので、ご褒美を設定しましょう。
たとえば

目標達成したら、SNSで話題のアノお店にケーキを食べに行こう!

目標達成したら、友達とひっさびさにカラオケ行こう!
など、なんでもいいのです。
励みになりますよ!

自分にご褒美をあげるって大事です!
4)情報を遮断する
SNSなどの情報を、たまに遮断することもオススメです。
デジタル・デトックス・ジャパンの情報によりますと次のようなデータが上がっているそうです。
データから見る事実
- 研究によると、落ち込み・ストレス・不安といった状態の人がデジタルデバイスを持たずに外出した結果、95%もの人がより平穏で、バランスの取れた気分に改善したと報告した。
- WHO(世界保健機構)はゲームのやり過ぎで日常生活に支障をきたす症状を正式に疾病と定義することを発表しました。
- 10代のスマートフォンでのインターネット利用は小学生で17.4%、中学生で46.4%、高校生で89.4%です。高校生の平日の平均利用 時間は177.7分でした。
- 平均的なユーザーはソーシャルメディアだけで1日平均2.15時間を費やします。(2012年時点では平均1.5時間)
- 2016年の調査では、スマートフォンを1日に150回(6分30秒ごとに)チェックし、毎日2,617回デバイスをタップし、スワイプしてクリックしています。
- 18歳〜34歳のほぼ半数が、ソーシャルメディアのフィードによって、自分は魅力的ではない、と感じている。
上のデータできになるのは、確実にSNSを見すぎると、自己肯定感が低くなりやすいということです。
気分が上がるのであればまだしも、落ち込むのだとしたら、情報を遮断して、自分の進む道をコツコツ進めていくほうが生産的です。

SNSをしばらく休んでも、死にやしません。
私も情報過多だな、と感じた時は、無理やり見ないようにしています。
まとめとして

あまりにも自分を「甘やかして」しまい、何も動かずに「いつか白馬の王子様来てくれる」日を夢見てもダメ、、、というか、残念ながら王子様は来ないです。
ですが自分に優しくしてあげることは大事です。
あなたはいつも頑張っています。
それをあなた自身が、ぜひ認めてあげてくださいね。
最後に、シュルレアリスムの代表的な画家であるサルバドール・ダリの言葉を。
完璧を恐れるな。
サルバドール・ダリ
完璧になんてなれっこないんだから。