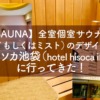Webサイトで「ピンク色」「肌色」がNGに?知っていて損はない安全な言葉選びと個人的見解
【景品表示法に基づく表記】本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。


カイエダです。
この記事では、昨今のWebサイト運営で意外と見落とされがちな「色の表現」についてお話しします。
現代のWebサイト運営において、言葉選びは非常に重要です。
特に、色を表す言葉一つで、サイトの印象やメッセージの伝わり方が大きく変わることがあります。
近年、「ピンク色」や「肌色」といった表現が、コンプライアンスの観点から注意が必要とされています。
これは一体どういうことなのでしょうか。
この記事では、Webサイトで色を表現する際の注意点と、誰にでも優しいWebサイトを作るための具体的な方法をお伝えします。
この記事の目次
「ピンク色」や「桃色」が持つ文化的・性的な含意と注意点
「ピンク色」や「桃色」と聞くと、多くの人は「可愛らしい」「優しい」といったポジティブなイメージを抱くかもしれません。
ですが、文脈や文化によっては、性的な意味合いや特定のイメージを強く連想させてしまうことがあります。
特に、日本の文化においては、ピンク色が特定の業界を連想させる場合があるため、現代のWebサイトの文脈での使用には注意が必要です。

ピンク色が持つ多面的なイメージ
ピンク色は、世界中で非常に多様な意味合いを持っています。
- 可愛らしさ、優しさ、女性らしさ:一般的に広く浸透しているイメージです。
- ロマンス、愛情:バレンタインデーなど、愛を伝えるシーンでよく使われます。
- 健康、若々しさ:肌の色が健康的に見えることから連想されることがあります。
- 特定の風俗:特に日本では、特定の場所やサービスを連想させる色として認識されることがあります。
このように、ピンク色はポジティブなイメージを持つ一方で、意図しないネガティブな連想を招く可能性(セクシャル・ハラスメント…通称セクハラ)も秘めているのです。
▼参考記事

「ピンク色」や「桃色」の具体的な代替表現
では、ピンク色や桃色を避けて表現したい場合、どのような言葉を使えば良いでしょうか。
- 淡い赤
- ローズ系
- コーラル
- マゼンタ
- サーモンピンク
- ベビーピンク
- 桜色(ただし、桜を連想させる場合に限る)
これらの表現は、より具体的に色味を伝えつつ、特定の連想を避ける助けになります。
色の名前がすでに一般的な場合もありますので、伝える相手に伝わりやすい表現を選ぶことが大切です。
Webサイトでピンク色や桃色を使う際の注意点
Webサイトでピンク色や桃色を使用する際は、その色が読者様にどのようなメッセージを伝えるかを慎重に検討する必要があります。
- ターゲット層の確認:ターゲットとなる読者様が、その色からどのような印象を受けるかを考慮します。
- 文脈と組み合わせ:色単体ではなく、使用するフォント、画像、文章の内容と組み合わせて、意図したメッセージが伝わるかを確認します。例えば、可愛らしい商品を紹介する際に、信頼感のあるデザインや言葉遣いと組み合わせることで、健全な印象を与えることができます。
- 過度な使用を避ける:特に、特定のイメージを強く連想させやすい場合は、メインカラーとしての使用を避け、アクセントカラーとして控えめに使うなど、工夫が必要です。
もし、不安を感じるようであれば、ピンク色や桃色にこだわらず、読者様に不快感を与えない別の色を検討することも賢明な選択です。
「肌色」という表現が使われなくなった理由と代替案
かつて、日本では当たり前のように使われていた「肌色」という言葉。
しかし、この表現は、世界中の多様な肌の色を考慮すると、特定の肌の色を基準にしているため、不適切であるとされています。
肌の色は人それぞれであり、一括りに「肌色」と表現することは、多様性を尊重する現代の価値観にそぐわないのです。
なぜ「肌色」はNGなのか?
「肌色」という言葉が定着したのは、特定の肌の色を指すクレヨンや絵の具の色名として使われ始めたことが大きいと言われています。
しかし、世界を見渡せば、肌の色は本当に様々です。この一見無害な表現が、無意識のうちに特定の肌の色を標準としてしまい、それ以外の肌の色を持つ人々を排除する可能性があるとして、見直されるようになりました。
さらに。
ピンク色と意味が近いですが、日本国内限定で「裸」を連想させる色として認知されています。
つまり「肌色」を使うと、裸であることの隠語みたいなイメージもあるんです。
それが特定業界を連想させたり、いかがわしさにつながるようです。

「肌色」の具体的な代替表現
では、「肌色」の代わりにどのような言葉を使えば良いのでしょうか?最も推奨されるのは、具体的な色名で表現することです。例えば、以下のような表現が考えられます。
- ベージュ
- ライトベージュ
- ペールオレンジ
- うすだいだい
- 薄いオレンジ色
- クリーム色に近い白
Webサイトで色を表現する際は、見たままの色を客観的に表現することを心がけましょう。
商品ページなどで色名を記載する際には、読者様に誤解なく伝えるためにも、具体的な色名を使うことが重要です。
Webサイト全体のジェンダーに配慮した表現ガイドライン
色の表現に限らず、Webサイト全体でジェンダーに配慮した表現を心がけることは、現代のWebサイト運営において非常に重要です。
これは、多様な価値観を持つ読者様全員に心地よく利用してもらうために不可欠な要素であり、結果としてサイトの信頼性やブランドイメージの向上にもつながります。
言葉遣いとテキスト表現
- 性別を特定しない表現:例えば、「担当者様」「皆様」のように、性別を限定しない言葉を選びましょう。「彼」「彼女」といった代名詞も、不必要に性別を強調しないよう注意が必要です。
- 職業や役割の表現:特定の性別を連想させるような表現(例:「看護婦さん」→「看護師さん」)は避け、性別に関わらず中立的な言葉を選びます。
- 多様な読者様を意識した表現:例えば、アンケートの選択肢に「男性」「女性」だけでなく、「回答しない」「その他」といった選択肢を加えるなど、多様な性自認を持つ読者様にも配慮した表現を心がけましょう。
画像やイラスト、デザインにおける配慮
- 多様な人々を描写する:画像やイラストを使用する際は、特定の性別、年齢、人種に偏らず、多様な人々を描写するように心がけましょう。例えば、ビジネスシーンのイラストでも、男女混合のチームや、様々な背景を持つ人々が登場するものが好ましいです。
…私は私の好みで笑、自分のブログでは偏った画像を使っていた!と少し反省です。 - 性別による役割の固定化を避ける:例えば、「男性は仕事、女性は家事」といったステレオタイプな描写は避けるべきです。
- アイコンやシンボル:ピクトグラムなど、性別を特定しないユニバーサルデザインのアイコンを選ぶと良いでしょう。
まとめとして
色の美しさとサイト運営のバランス
今回のテーマでお伝えしたかったのは、当然ですが色そのものに優劣はないということです。
どんな色も、それぞれが持つ美しさ、強さ、個性があります。
ピンク色も、肌色に近い色も、その色自体が悪いわけでは決してありません。
そして、色に特別な思い入れや、文化背景を感じさせる色彩心理があること自体、なんだかこう、人間らしい愛しい部分だと私は思うんですよ。
ですが。
昨今の社会情勢や多様な価値観が尊重される流れの中で、色から連想されるイメージが非常に強くなっているのも事実です。
Webサイトは不特定多数の読者様が訪れる場所です。
言葉選びには慎重にならざるを得ないのが現状です。
これは、決して「この色は使ってはいけない」という話ではありません。
過去の事例や社会の変化を見ながら、読者様に不快感を与えないための配慮が必要なのです。
▼参考記事

それぞれの色が持つ魅力を理解した上で、表現方法を工夫していきましょう。
そうすることで、読者様にとってより安心で心地よいWebサイトを運営できるはずです。